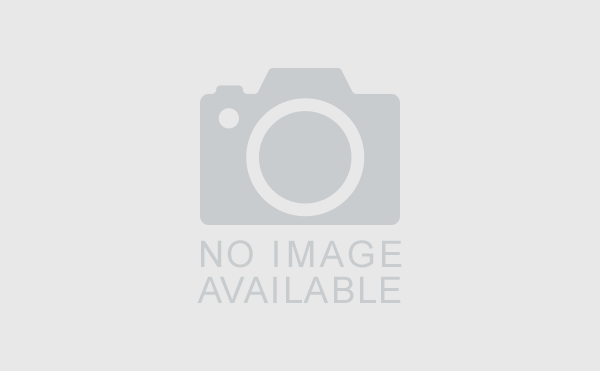座布団投げは、是か非か。そのルーツを探る。
相撲を観ていると、理由はよく分からないが定型化されている動きや文化が非常に多い。
例えば力士の仕切りや土俵入り、
弓取り式や塩まき。
相撲関連の書籍やウェブサイトを確認すると全てに於いて意味が有り、また長い歴史が有ることがよく分かる。
それらの一つ一つが文化であり、相撲というのはそうした文化の集合体だと実感する。
相撲というのはスポーツや興行である以前に神事であり、平安時代には朝廷で定期的に相撲節として行われていた、などという説明を聞くとこれらの背景についても納得がいく。
だが、こうした背景を持つ相撲にしては
ひとつ納得がいかない風習が有る。
そう。
座布団投げである。
勝って奢らず、負けて腐らず。
勝って兜の緒を締めよ。
見た目の結果もさることながら、観る者も力士も精神性を重んじ、相手や土俵にすら感謝する。
そういう文化でありながら、波乱が起きたら座布団を投げるのだ。
横綱という土俵上の神に対するリスペクトも感じないし、神聖なる土俵を汚すことにも繋がる。
誰もが子供に帰って等しく一喜一憂する、という醍醐味の一つではあるし、座布団が舞う光景は一種の美のように感じることも有る。
だが、文化としての一連の所作や精神性と比較すると座布団投げだけが異質なのだ。
というわけで、私は座布団投げの背景について調べてみた。すると、複数のソースで共通の事象が出てきた。
現在の座布団投げとは異なるが、明治時代に贔屓力士が勝利した際に半纏など、力士名が特定できるものを投げ込むという風習が有り、力士や呼び出しが返却する際にご祝儀を与えていたとのこと。
ルーツといえばルーツに見えなくもないが、共通項は何かを土俵に投げ込んでいるということであって、その背景に有る理由は全く異なる。
ちなみにこのご祝儀の流れを現代に継ぐのが懸賞金のシステムだという。
力士個人にタニマチ的に出資するだけでなく、広告的な価値を提供する、というのは現代的な進化と言えるのかもしれない。
座布団を投げる、モノを投げ込むということが現代的な行為なのではなく、かなり昔から継続的に行われてきた風習なのだということは理解できた。
これを粋と捉えるか、無粋と捉えるかは
個人の感覚にも依るだろう。危険とも下品とも理解できる行為ではある。
一つはっきりしているのは、観る側のこうした感性は今も昔も変わり無く、現代のファンが幼稚になったから行われている行為ではない、ということである。
だとすると、今は顔をしかめて観られることも有る力士の名前を書いた紙や手拍子、~コールという行為も今後は一つの文化として残っていくのかもしれない。
…いつの時代も議論の的には成ると思うが。